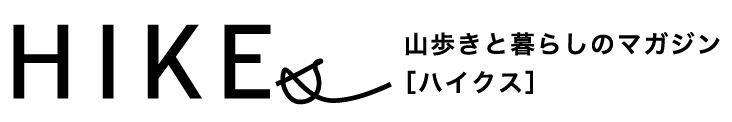日帰り登山を何度か経験して山歩きに慣れてくると、次に気になってくるのが「山小屋泊」です。朝焼けや夕焼けを眺めたり、山仲間と語り合ったりと、山で一夜を過ごすことで日帰りでは味わえない静かで特別な時間を体験できます。
テント泊に比べて荷物も少なくて済むため、日帰り登山に慣れてきた方であれば無理なくチャレンジできるのも魅力です。
とはいえ、初めての山小屋泊には不安もつきもの。「どんな服装で過ごせばいいの?」「お風呂はあるの?」「食事はどうするの?」など、分からないことも多いですよね。
この記事では、山小屋泊が初めての方に向けて、過ごし方や持ち物、服装のポイントなどをわかりやすくご紹介します。
山小屋とはどんなところ?山小屋の種類

「山小屋」と聞いて、山頂付近にあるログハウスのような建物を思い浮かべる方も多いかもしれません。けれど、実際の山小屋は立地や設備によってさまざまなタイプがあります。まずは、山小屋の基本的な役割や種類について整理しておきましょう。
山小屋とは
登山で使われる「山小屋」とは、登山行程の中で宿泊や休憩、食事などができる山中の施設のことを指します。大きく分けて「有人の山小屋」と「無人の避難小屋」の2つに分かれます。
有人の山小屋は、管理人やスタッフが常駐していて、予約制で宿泊ができる施設です。夕食・朝食の提供や、寝具の貸し出しなどがあるのが特徴で、宿泊料を支払って利用します。
無人の避難小屋は、基本的に無料で利用できますが、寝具や食事の提供はなく、すべて自分で用意する必要があります。悪天候時の避難所として設けられているため、宿泊目的というよりは「緊急時に使う場所」と考える方がよいでしょう。
また、同じ「山小屋」といっても設備はさまざまで、有人小屋であっても食事が軽食のみだったり、寝具がない場合もあります。利用前には公式サイトやガイドブックなどで、設備の有無やサービス内容をしっかり確認しておきましょう。
ちなみに、山小屋の名称は「○○小屋」だけでなく、「○○ヒュッテ」「○○荘」「○○ロッジ」などさまざまです。呼び方が異なっていても、登山者が宿泊・休憩に使う施設という点では、すべて「山小屋」として総称されます。
山小屋の予約について
山小屋に宿泊する際は、原則として事前予約が必要です。食事の準備や部屋割りの都合があるため、特に登山者が増える7〜10月のシーズン中は早めの予約をおすすめします。
山小屋は、悪天候や体調不良といった緊急時に命を守る場でもあるため、基本的に「予約がないから泊まれない」と断られることはありません。しかし、だからといって無断で訪れるのはマナー違反です。トラブルを避けるためにも、よほどの事情がない限りは必ず事前に連絡・予約をしておきましょう。予定変更で行けなくなった場合も、必ずキャンセルの連絡を入れてください。
予約方法は山小屋によって異なり、Web予約ができるところもあれば、電話でのみ受け付けている小屋もあります。各施設のホームページや登山情報サイトなどで、予約方法を事前に確認しておくと安心です。
また、山の中では電波が届きにくかったり、食事の仕込み中で電話に出られないこともあります。「電話がつながらない!」と焦らず、昼過ぎの時間帯にかけ直すとつながりやすい傾向があります。大規模な山小屋では登山口付近に事務所があることも多く、そちらに連絡するのも一つの方法です。
山小屋での服装は?山小屋泊の荷物を確認しよう
事前予約が済んだら、次は装備と持ち物の準備です。初めて山小屋泊にチャレンジする方にとっては、「日帰り登山と何が違うの?」「何を持っていけばいいの?」と悩むことも多いはず。山での宿泊となると、必要な荷物は日帰りの時よりもやや多めになります。
ここでは、夏に1泊2日で山小屋泊をする場合を想定した基本の持ち物を紹介します。行く山の標高や気候、季節によって必要な装備は変わってくるため、必ず自分の登山計画に合わせて調整してください。
【基本装備】
山小屋泊は日帰り登山より装備が増えるぶん、持ち歩く基本装備の選び方が重要になります。安全と快適の土台となるギアは、あらためて丁寧にそろえておきましょう。
項目 | 重要度 | 備考 |
|---|---|---|
登山靴・トレッキングシューズ | ◎ | 履き慣れたもの。防水性とグリップ力があると安心 |
ザック | ◎ | 25ℓ以上が目安。着替え・食料・防寒具なども入るサイズ |
ザックカバー | ◎ | 急な天候変化に備えて。必ず携帯 |
レインウェア | ◎ | 防寒と雨対策を兼ねる必須装備 |
地図 | ◎ | 紙の地図はスマホの電池切れ時にも有効 |
コンパス | ◎ | 地図とセットで使用。現在地の把握やルート確認に |
ヘッドランプ | ◎ | 夜間の移動や万が一の下山遅れに備えて |
腕時計 | ◯ | 時間管理に。気温差の大きい山では行動時間が重要 |
ポイント
25ℓ以上のザックで余裕を確保
1泊分の荷物を無理なく収納するには、日帰りより少し大きめのサイズが必要です。
レインウェアは“防寒着”としても使える
雨が降らなくても、風除け・体温調整に使える万能装備です。
ヘッドランプは忘れがちだけど必須!
夜間トイレや早朝出発など、山小屋泊ならではの行動に必ず役立ちます。
【服装】
山小屋泊では行動中の服装に加え、夜間の冷え込みや翌朝の行動も視野に入れた服選びが大切です。汗をかいた後の着替えや、軽量な防寒対策は快適な1泊2日を支えてくれます。
項目 | 重要度 | 備考 |
|---|---|---|
肌着(ベースレイヤー)×2 | ◎ | 吸汗速乾タイプ。当日と翌日の着替え用で2枚あると快適 |
Tシャツ×2 | ◎ | 速乾素材がおすすめ。宿で着替えると寝心地も◎ |
パンツ | ◎ | ストレッチ性・速乾性がある登山用。基本的に替えは不要 |
下着 | ◎ | 汗で蒸れやすいので着替え用含めて2枚。速乾素材が安心 |
中間着(ミドルレイヤー) | ◎ | フリースや厚手のシャツなど、保温と通気を兼ねた軽量モデルが理想 |
防寒着 | ◎ | 夏でも朝晩は冷えるため、薄手のダウンやインサレーションを携帯 |
帽子 | ◎ | 熱中症・日焼け防止に。通気性とフィット感重視 |
ソックス | ◎ | 靴ずれ・冷え防止に厚手でクッション性のあるもの。替えも必須 |
手袋 | ◯ | 転倒や岩場の怪我防止に。風よけ・寒さ対策としても使える |
【サポート装備・持ち物】
あると便利な装備類は、登山中のトラブル回避や快適性を支えてくれる心強い味方。ただし、持ちすぎは重量増に繋がるため自分に必要なものを見極めて選びましょう。
項目 | 重要度 | 備考 |
|---|---|---|
トレッキングポール(ストック) | ◯ | 下りや長距離歩行で膝の負担軽減に有効 |
ゲーター | △ | 小石やぬかるみの侵入を防ぐ。特定の山域や悪天候時に活躍 |
ショルダーバッグ・ウエストポーチ | ◯ | スマホ・行動食などすぐに取り出したい物を収納できて便利 |
サングラス | ◯ | 紫外線や雪面の照り返しから目を保護。高山では必須レベル |
タオル・手ぬぐい | ◎ | 汗拭き、日よけ、ケガの応急処置にも。薄手で乾きやすいものが◎ |
お金(小銭) | ◎ | 山小屋の支払いや自販機利用に。お釣りが出ないよう事前に準備を |
日焼け止め | ◯ | 特に顔・首・手の甲はしっかりガード |
ファーストエイドキット | ◯ | 絆創膏・消毒液・常備薬・テーピングなど、自分用にカスタムを |
携帯電話 | ◎ | 地図・時計・連絡手段として多機能。飛行機モードで節電を |
携帯電話の充電器(モバイルバッテリー) | ◯ | 予備電源として。小型軽量タイプが登山向け |
身分証明書 | ◯ | 緊急時に本人確認ができるように。保険証コピーもあると◎ |
カメラ | ◯ | 思い出の記録に。スマホ併用でもOK |
体拭きシート | ◯ | 山小屋に風呂がない場合のリフレッシュ用 |
歯ブラシ・歯磨き粉 | ◯ | 歯磨き粉は水場で使用NGのこともあるため、持ち込みは要確認 |
耳栓・タオル(枕カバー代用) | △ | 雑音対策。大部屋泊の快眠サポートに |
ビニール袋(ゴミ袋) | ◯ | ゴミや汚れ物の収納用。防水インナーとしても代用可 |
メイク落としシート | ◯ | 女性向け。ウェットティッシュ代わりにも |
メイク用品 | ◯ | 必要最小限に。軽量・コンパクトが基本 |
ポイント
あると安心と軽量化のバランスが大事
快適さの追求も重要ですが、荷物はできるだけシンプルにまとめるのが理想。
山小屋利用でも現金・小銭は必須
山の中ではクレカ・電子マネーが使えないことが多いので要注意。
タオル・手ぬぐいは万能選手
汗・寒さ・応急処置・枕カバー代わりと、1枚で何役もこなせます。
【食料】
山小屋泊では、基本的に食事が提供されるプランが多いため、自分で調理する場合を除けば大きな装備は不要です。ただし、お昼ごはんや行動食・非常食は忘れずに。軽くてカロリーのある食品を選びましょう。
項目 | 重要度 | 備考 |
|---|---|---|
水 | ◎ | 最低1ℓは携行。調理や予備も考えるならもう少し多めに |
行動食 | ◎ | ナッツ、チョコ、エネルギーバーなど小分けで食べやすい物 |
非常食 | ◎ | 行動不能時を想定。日持ちするカロリー高めの食品を |
1日目のお昼ごはん | ◎ | おにぎり、パン、カップ麺など調理しなくても食べられる物 |
コーヒー | △ | 景色のいい場所での“ひと息”に。ドリップやインスタントでOK |
ポイント
水分は最優先で確保!
山では思った以上に汗をかきます。最低1ℓ+予備が安心。
行動食は“すぐ食べられるもの”を複数持つ
行動中に止まらず補給できるのが理想。甘いもの・塩分系をバランスよく。
非常食は“使わなくてもいい”のが理想
でも持っていることが安心材料になります。個包装で賞味期限が長いものを。
山小屋泊に慣れないうちは「これも必要かも」と不安になって、つい荷物が多くなりがちです。でも、何度か経験を重ねていくうちに、自分にとって本当に必要なものと、そうでないものが少しずつ見えてきます。
ここでご紹介した装備や持ち物は、あくまで目安です。すべてを完璧に揃える必要はありません。回数を重ねながら自分の登山スタイルや体力、快適さのバランスに合った“ちょうどいい荷物”を見つけていきましょう。
また、山小屋の枕や寝具が気になる方は、枕カバー代わりのタオルやシュラフシーツ(寝袋用のインナー)を持参すると安心です。軽くてかさばらないので、清潔さや快適さを重視する人にはおすすめのアイテムです。
そのほか、個人のスタイルに合わせた小物類。例えば、メイク落としシートやリップクリームなど、日常的に使っているケア用品もあると安心です。必要最低限に絞って、小さな容器に詰め替えて持っていくのがおすすめです。
山小屋泊では、“ちょっとした備え”が快適さにつながります。無理なく自分にとって心地よい準備を心がけてみてください。
山小屋に到着したら、まず何をすればいい?1日の流れ
はじめての山小屋泊では、「到着したらどう動けばいいの?」と戸惑うこともあるかもしれません。ここでは、山小屋到着後の過ごし方を時系列に沿ってご紹介します。事前に流れを把握しておくことで、安心して山の時間を楽しむことができます。
山小屋には15時までの到着が基本
山小屋には、遅くとも15時までに到着するのが基本です。夕方以降は天候が変わりやすく、暗くなると道に迷うリスクも高まるため、安全のためにも早めの行動を心がけましょう。
万が一、予定より遅れる場合は山小屋に必ず連絡を。スタッフの方も無事の確認ができず不安になりますし、連絡があるだけで対応もしやすくなります。
山小屋の受付でチェックイン
到着後はまず受付へ。予約者名を伝えて料金を支払いましょう。多くの山小屋では現金払いのみなので、小銭も含めて準備しておくとスムーズです。
このときに、食事の時間・館内設備・部屋の場所などの説明を受けます。一部の山小屋では、予約順ではなく到着順に部屋を割り当てることもあるため、早く到着するに越したことはありません。
なお、宿泊料金にはトイレの使用料も含まれていることが多いため、別途支払いは不要です(※小屋によって異なる場合あり)。
着替え・荷物整理は早めに
部屋に案内されたら、まずは濡れた服や汗をかいたインナーを着替えましょう。基本的に更衣室はないため、仕切りカーテンのある場所や布団の中、トイレを活用するのが一般的です。
お風呂のない山小屋も多いため、着替えの際に体拭きシートなどでさっぱりしておくと快適に過ごせます。夜は冷えやすいので、防寒を意識したリラックスウェアに着替えて体を休めましょう。
雨で濡れたウェアは、乾燥室があれば活用を。干しっぱなしにせず、乾いたら取りに行くなど、他の登山者への配慮も忘れずに。
ザックは汚れを落としてから、人の通行を妨げない場所に置きましょう。また、必要な物(貴重品やヘッドライトなど)はサブバッグにまとめておくと、移動の際に便利です。
山小屋での夕食は早めが基本
夕食は、17時〜18時頃に提供されることが一般的です。多くの山小屋では食堂での一斉食事となり、混雑時は時間を分けて対応する場合もあります。チェックイン時に時間を確認しておきましょう。
自炊をする場合は、山小屋の食事時間終了後に調理可能な施設があるケースが多く、食堂や屋外の自炊スペースが使えます。山小屋のルールに従って静かに行いましょう。
なお、早朝に出発する予定がある方は、夕食時に翌朝用のお弁当を受け取れることもあります(※要予約・山小屋により異なります)。必要な方は事前に確認・依頼しておきましょう。
登山者同士の“山時間”を楽しんで
山小屋では、登山者同士で自然に会話が生まれることも少なくありません。山の情報を共有したり、翌日のルートを相談したり。静かな時間を過ごすのも、山小屋泊ならではの魅力です。
自炊をしている人の姿を見て「次は自分もやってみたい」と思うことも。余裕ができたら、山ごはんにチャレンジするのも、登山の楽しみを広げるきっかけになりますよ。
消灯。早めの就寝で明日に備えよう
ほとんどの山小屋は21時に消灯。ヘッドランプや明日の荷物をあらかじめ準備しておくと安心です。耳栓やアイマスクがあると、より快適に眠れますよ。山小屋泊は、早寝早起きが基本。静かな夜の山を感じながら、体をしっかり休めましょう。
山小屋ではどうやって過ごせばいいの?
山小屋での過ごし方に“正解”はありません。静かな山の時間を、本を読みながらゆっくり楽しむ人もいれば、外に出て星空を眺めたり、同じ小屋に泊まった登山者と会話を楽しむ人もいます。
ただし、山小屋はみんなで使う共同スペース。お酒を飲んで大声を出す、大音量で音楽を流すなど、まわりに迷惑がかかる行動は避けましょう。小さな気づかいが、お互いに気持ちよく過ごすためのコツです。
では、ほかの登山者は実際にどんなふうに過ごしているのでしょうか? 山小屋泊の経験がある方々に、過ごし方を聞いてみました。
山小屋泊経験者に聞きました。山小屋泊での空き時間はどう過ごしますか?
取材協力:ミルトーク(このアンケート結果はミルトークより引用しております)
40代 男性
休む前にストレッチやマッサージで体をほぐし、身に着けているものも緩めて、できるだけリラックスして体を休めること。
50代 女性
山小屋に着くとすぐにカレーの夕食です(ほとんどのメニューがカレーのみ)。食後は次の日の日程を確認します。早朝には下山することが多いので早く寝ます。
50代 女性
サークルで行っていたので10人前後のグループでした。星空を見ながら歌を歌ったりゲームをしたり、軽くストレッチをして翌日に備えて早めに寝ました。
30代 女性
混んでいたし疲れていたので、足に疲れを取るシートを貼って、マッサージをしてすぐ寝ました。
50代 女性
体が冷えないように軽くストレッチをしたり、お話をしたりしていました。翌朝は早いので早めに寝て体の疲れをとるようにしていました。
40代 女性
リンパマッサージをして、湿布をして、明日に備えて早く寝ました。
30代 女性
水分を意識して取り、足のマッサージと持ち物のチェックとメンテナンスを行います。
ポイント
全体を通して、「体を休めて早めに寝る」「翌日の準備をしておく」という声が多く見られました。
山小屋の夜は、翌朝の登山に向けた大切な“回復タイム”でもあります。自分に合ったリラックス方法を見つけて、静かな山の夜を楽しみましょう。
山小屋で快適に眠るためのポイント
夕食を終えてゆっくり過ごしたら、いよいよ就寝時間です。山小屋では基本的に21時ごろが消灯。山の朝は早いため、夜も早めに休むのが基本です。消灯後は真っ暗になりますので、寝る前に必要な準備を整えておきましょう。
消灯前にしておきたいこと
- ヘッドライトをすぐ使える状態に
トイレや移動のために、手の届く場所に置いておきましょう。出発前に電池の残量も確認を。 - 水を枕元に用意
夜中に喉が渇いたときのために、飲み物はすぐ取れる場所に置いておくと安心です。 - 歯磨きは水だけで
歯磨き粉の使用は基本NG。水でブラシを濡らして軽く磨くのがマナーです。 - 朝の支度を時短する工夫を
乾かしていたウェアの回収や荷物の整理は、消灯前に済ませておくのがおすすめ。朝がスムーズになります。 - ストレッチで体をリラックス
血行をよくしておくことで、寝つきが良くなり疲労回復にもつながります。
就寝時の服装と過ごし方
寝るときは、体を冷やさない服装を選びましょう。夏でも標高が高い山小屋は冷えることがあるため、フリースやダウンなど軽めの防寒着があると安心です。
翌朝の出発が早い場合は、登山ウェアのまま寝ることで、朝の準備がぐっと時短になります。
また、以下のアイテムも役立ちます。
- 耳栓
いびきや物音が気になる方におすすめ - タオル
枕代わりに、または寒さ対策に使えます
夜中に目が覚めてしまっても焦る必要はありません。目を閉じて横になっているだけでも体と脳はしっかり休まります。翌日の登山に備えて、できるだけリラックスした状態で眠りましょう。
山小屋泊の朝
山小屋の朝は早く、まだ外が暗いうちから周囲でごそごそと準備を始める音が聞こえてきます。多くの登山者が朝5~6時の朝食に合わせて4時頃には起床し、ストレッチや荷物の整理、歯磨きや洗顔を済ませます。なかには3時台に出発してご来光を目指す人もいるため、山小屋全体が静かに慌ただしくなる時間帯です。
洗面所や通路など共有スペースでは譲り合いが大切です。準備はなるべく静かに行い、まだ休んでいる人の迷惑にならないよう心がけましょう。
山小屋泊でしか味わえない朝日を見よう!
山小屋泊ならではの楽しみのひとつが、山から望む朝日です。空が白み始める頃、東の空がだんだんと赤く染まり、雲海の上に朝日が昇っていく光景は、言葉にできないほど美しいものです。場所によっては、山肌が赤く照らされる「モルゲンロート」と呼ばれる現象も見られます。
「朝は寒くて外に出るのが億劫」と感じる方も多いですが、朝の冷たい空気の中で見る朝日は格別です。防寒対策をしっかり整えたうえで、外に出てみることをおすすめします。
山小屋の朝ごはん
朝ごはんは夕食と同様に決められた時間に食堂で提供されるスタイルが一般的です。和食中心のメニューが多く、ごはん、味噌汁、焼き魚、漬物など、シンプルながらエネルギーと栄養をしっかり取れる内容になっていることが多いです。
朝から長時間歩く登山では、空腹でスタートするのは避けたいもの。朝食が提供される場合はしっかり食べておきましょう。お弁当を予約している場合は、このタイミングで受け取れることが多いので、忘れずに確認してください。
山小屋でのチェックアウト
山小屋のチェックアウトは、すでに宿泊費を支払い済みであれば特別な手続きは必要ありません。出発時には、使用した布団を整え、部屋を軽く清掃し、ゴミはすべて持ち帰るのが基本マナーです。
スタッフの方に「お世話になりました」とひと言声をかけて出発できれば、気持ちのよい山旅の締めくくりになります。出発前に水の補給ができる場合は、必要分を補充しておくと安心です。
また、山小屋によってはオリジナルの手ぬぐいやバッジなどの記念品を販売していることもあります。思い出として一つ買っておくのも楽しみのひとつです。
初心者にやさしい、快適な山小屋5選
初めての山小屋泊なら、設備が整っていて安心感のある山小屋を選ぶのがポイントです。ここでは、登山初心者でも泊まりやすく、快適に過ごせる山小屋を5つご紹介します。アクセスしやすく、人気の山域にありながらも、比較的落ち着いて過ごせる場所を中心に選びました。
① 燕山荘(北アルプス)

北アルプス・燕岳に位置する「燕山荘(えんざんそう)」は、初めての北アルプス登山にもぴったり。ケーキが楽しめる喫茶室や、アルプホルンの演奏イベントなどがあり、山小屋とは思えないほど快適。女性登山者にも人気の山小屋です。
- 【営業期間】4月中旬〜11月中旬 ※年末年始も営業
- 【料金】1泊2食付き ¥10,000(税込)
- 【収容人数】650人
- 【個室】あり(要予約)
- 【テント場】約30張/1名 ¥700(税込)
- 【軽食】あり(喫茶スペースあり)
- 【トイレ】水洗あり
- 【ホームページ】燕山荘ホームページ
② 赤岳鉱泉(八ヶ岳)
.webp)
南八ヶ岳の人気ベース地「赤岳鉱泉(あかだけこうせん)」は、通年営業で冬の登山者にも支持されている山小屋です。食事の評判が高く、なんとお風呂付き。冬は氷で作られたアイスキャンディーも有名です。
- 【営業期間】通年
- 【料金】1泊2食付き ¥9,000(税込)
- 【収容人数】250人
- 【個室】あり(要予約)
- 【テント場】約30張/1名 ¥1,000(税込)
- 【軽食】あり(食堂兼喫茶あり)
- 【トイレ】水洗(暖房便座付き)
- 【ホームページ】赤岳鉱泉ホームページ
③ 銀嶺荘(ぎんれいそう(乗鞍岳)

標高2,700mを超える乗鞍岳の畳平に位置する「銀嶺荘(ぎんれいそう)」は、アクセス性と快適性を兼ね備えた初心者にもやさしい山小屋です。風呂や売店、水洗トイレなどの設備が整い、個室利用も可能。乗鞍岳・剣ヶ峰へは約45分で登頂でき、夏は高山植物、秋は紅葉、夜には満天の星空を楽しめる贅沢な立地が魅力です。
- 【営業期間】7月1日~10月17日(※10月は積雪により休館の場合あり)
- 【料金】1泊2食付き
- 1名部屋:¥23,000+税
- 2〜3名部屋:¥14,000+税
- 4名以上部屋:¥11,000+税
- 【子ども料金】
- 12歳未満:¥16,100(1名部屋)/¥9,800(2〜3名)/¥7,700(4名〜)+税
- 未就学児(添い寝・食事なし):¥1,000+税
- ・1歳未満:無料
- 【収容人数】非公開
- 【個室】あり(要予約)
- 【テント場】なし
- 【軽食】売店あり(おにぎり・ドリンク・お菓子など)
- 【トイレ】水洗あり(共用)
- 【入浴時間】17:00~20:00(男女別・各6〜7名まで同時入浴可)
- 【ホームページ】銀嶺荘 公式サイト
④ 三斗小屋温泉・煙草屋旅館(那須岳)

那須岳の静かな山中に佇む「煙草屋旅館(たばこやりょかん)」は、三斗小屋温泉にある秘湯の山小屋。趣ある木造建築と、自然に囲まれた露天風呂が魅力です。まるで山奥の温泉旅館に来たような快適さが味わえます。
- 【営業期間】4月中旬~11月末
- 【料金】1泊2食付き ¥9,000(税込)
- 【収容人数】100人
- 【個室】あり(要予約)
- 【テント場】3張/1泊 ¥2,000
- 【軽食】なし(飲料販売あり)
- 【トイレ】水洗あり
- 【入浴時間】
- 露天風呂:15:00~17:00(女性専用時間)
- 共同浴場:18:00~19:00(女性専用時間)※全体利用は20:00まで
- 【ホームページ】三斗小屋温泉・煙草屋旅館ホームページ
⑤ 涸沢ヒュッテ(北アルプス)

涸沢カールの絶景を望める「涸沢ヒュッテ」は、北アルプスの人気スポットにある山小屋です。テラスから見上げる穂高連峰の景色は圧巻。山上で味わう生ビールも人気で、登頂後のご褒美にぴったりです。
- 【営業期間】4月下旬~11月上旬
- 【料金】1泊2食付き ¥9,500(税込)
- 【収容人数】180人 ※混雑期は相部屋・相布団になることも
- 【個室】なし
- 【テント場】1泊 ¥500(レンタルあり・要予約)
- 【軽食】あり
- 【トイレ】あり
- 【ホームページ】涸沢ヒュッテホームページ
- 【備考】繁忙期は大混雑必至。ゆったり過ごしたい方はテント泊も検討を。
山小屋泊は「不便さも楽しむ」山の特別な体験
山小屋泊の魅力は、何といっても日帰りでは出会えない景色や時間にあります。夕日に染まる山々、静寂のなかで迎えるご来光、満天の星空。これらは、実際に泊まってこそ味わえる特別なひとときです。
ただし、山小屋は自然のなかにある特別な環境。水や電気などの設備が限られており、決して快適とは言えない場面もあります。事前に情報をよく確認し、準備しておくことで、「こんなはずじゃなかった…」というギャップを避けることができます。
初めて山小屋に泊まるときは、無理せず、仲間と一緒に難易度の低い山域を選ぶのがおすすめです。最近では、温泉付きや食事が評判の山小屋など、個性的な小屋も増えており、山小屋自体を目的に登山を楽しむ人も増えています。
山に慣れてきたら、ぜひ一度、山小屋泊にチャレンジしてみてください。山で過ごす一夜が、あなたの登山体験をさらに豊かにしてくれるはずです。
山小屋泊には揃えておきたい登山道具